COCODECO NETWORK
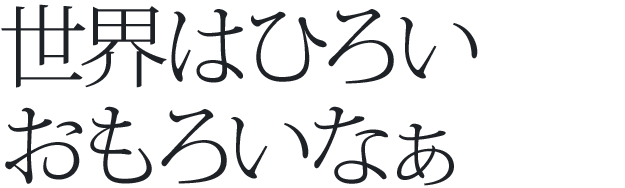
私たちには、海外で活躍されている親しい友人たちがたくさんいます。
私たちは彼らのことを「ワールド ワイド ワード」(Web?笑)と呼んでいます。
メンバーから寄せられる、ちょっと目線の違う独自のニュースをご覧ください。
男のパンツ(英国:ボストン発)今回のテーマは「パンツ」。
BBC放送の名物ジャーナリストでありアンカーマンのジェレミー・パクスター氏(57歳)。ゲストの話をさえぎり容赦なしの鋭い質問を放り投げて相手を突き放す様はこちらがハラハラ。執拗に同じ質問を投げて、つかみどころなくごまかそうとするゲスト(政治家のことが多い)を追いつめるスタイルは無情の主尋問者。あまりの無作法ぶりにBBC放送に視聴者から苦情が殺到したこともあるとか。
その彼が不満だとぶちあけたのが、大手小売チェーン・マークス&スペンサー(M&S)の「パンツ」。年俸億単位と言われるパクスター氏であるが、下着はM&Sで調達しているらしく、その質の低下=サポートの頼りなさに不満ありと、M&Sの最高経営責任者ローズ卿にメールを送ったというのが話題に。
そこから波及して、男性パンツの歴史や、好みのタイプ、ブランドパンツの推移といったパンツ談義が展開。所詮、込み入った話よりもお気楽モードにスイッチしやすい私、荒れる金融市場の記事に目を通しているつもりが、ついつい横目に入ってくるパンツ記事を読んでしまったという次第。
M&Sは1884年創立のイギリスを象徴するスーパーで、食品から衣類や家庭用品まで自社ブランドのみを扱う。イギリスッぽさを求めて大陸からの観光客がめざす店とも。トルコ人友人がイギリス土産といえばココなのよと、高級デパートのハロッズやリバティーには目もくれずにひたすら買い物をしていたのを思い出す。
1990年後半に経営不振に陥ったが、その後立て直し。食品部門は3年ほど前から前出のローズ卿が進めたTVコマーシャル宣伝がヒット。ゆったりした音楽が流れる中、クローズアップで映しだされる焼いたホタテとスペイン製チョリソー、一口サイズのとろけるチョコレートがしたたるベルギー産チョコレートプディング…。そして甘い女性のささやく声で「This is not just food, it's M&S food」。そこらのフーズとはちと違うのだと強調して高級感たっぷり。他社によるパロディ版コマーシャルも出たほどで、2006年には最も印象的・効果的だったとして広告賞も取っている。
レンジやオーブンものの加工食品はイギリス人に根強い人気。サンドイッチともなると想像を超えた組み合わせもあって種類豊富で、金融街シティにあるM&Sの昼時はどこもレジの前に長蛇の列ができる。また肉野菜やフルーツ類となると、テスコやセインズベリーズなどの格安量販店大手スーパーとは格の違いを見せつけるかのように高級路線である。上流階級も買い物にくるが(除く・衣類)、低所得者層には敷居が高めといった位置づけ。
衣類(特に婦人服)はそのイギリスらしさが一時はダサいとも言われて苦戦したこともあるが、ここ数年は大規模なてこ入れで衣類部門を一新。高級ブランドにも負けじと新ラインの開発、細かく体型ごとに選べるラインや、人気女優やタレントで宣伝にも力を入れて随分とイメージチェンジが進んでいる。その分、男性下着・靴下部門が手抜きとなったのか?
パンツのサポート感不足のみならず(きつすぎず、ゆるすぎずの度合いが難しいらしいですな)、靴下も破れやすいのはいかがなものかとパクスター氏。同じ不満を持っている男性がタンといたようで、BBCの辛口アンカーマンの率直なオピニオンに同感、よくぞ指摘してくれましたとばかりに盛り上がり、一躍M&Sで下着・靴下を購入するイギリス男性の代弁者となった格好である。
ハイストリートのデパートで買うほどでもないが、野菜や家庭用品が売られるフロアの隅に設けられたコーナーで格安下着を買うのはさみしいという、イギリス中流男性にとっては、老舗M&Sは心のよりどころ、安心して「いつもの質の良いアレ」が買えるところでないといけないのである。
さて、メールを受け取った最高責任者ローズ卿はどう受けて立つのかといえば、パクスター氏を昼食に招待、パンツの伸縮性やサポート具合について話し合うのだとか。
パンツとなると、実は女性よりも繊細なのではといわれる男性陣。アンダーバストからカップサイズまで細かい女性のブラほどサイズが細かくないのはその繊細さゆえとも。誰かが言っておりました、「腰まわり○○センチ、サイズAのパンツをください」とは男性は言えないのだと。なるほど。
卵が先か、キャリアが先か(英国:ボストン発)先月、思い立ったが吉日と、大学院時代の友人を訪ねて香港へ飛んだ。
何度か訪れてはいるが、欧州のカラ天気に慣れた老体(?)には5月の香港は予想以上にきつく、湿気を多く含んだ熱気とガンガンに冷えたビル内の温度差にびくびくしながら、カーディガンで温度調整。そんな中、せわしなさと同時に、得体の知れない度胸と自信に満ちた活気に「そうそう、コレが香港」と再認識。今回は、コンビニやドラッグストアで日本製品がごく普通に混在し、当たり前に購入されていく様子が私にとっては珍しく、久々の○○屋の牛丼が嬉しかった。
香港の金融機関で働く友人は中国本土やシンガポール、インドなど多くの出張をこなすキャリアウーマン。さらなるキャリアアップをめざして転職先を探しているところなのだが、久々に会って弾む会話の中で彼女の口から出た言葉が、「いつ子供を作ろうかしら?」。決まった相手はいるものの、シングルの彼女。しかも、共通の友人Aもシングルながら『子作り』真っ最中で時々情報交換をしているのだという。
共通の友人Aとは同じロンドン在住ながらすっかりご無沙汰している懐かしいクラスメート。
香港経由で彼女の連絡先を知ることとなり、さっそく、インターネットでロンドンのAと、香港のわれわれ2人がチャットとなった。
「今日から2日間が勝負、彼を寝室に監禁状態よ」というA。
40歳が視野に入ってその緊急度を認識したと言う。Aには、離婚暦あり・子供ありのイギリス人男性の彼がいる。入籍はまだだが、自分の子供が欲しいという彼女。成功率が高いと聞いたスペインのクリニックで体外受精治療も受けてきたものの成功せず。今は婦人体温計片手に自宅寝室作戦に切り替え励む毎日。その大事な2-3日がやってきたようだ。
『四捨五入30歳』つまり25から34歳ぐらいまでが、「ウェディングベルを鳴らすか鳴らさないか、もしくは鳴らせないか」の乙女の悩める時期なら、『四捨五入40歳』は「子供を産む、産まない、もしくは産めない」の重大な選択もしくは事実に直面する卵の悩める時期といったところか。
「子供が欲しいならYoも今のうちよ」という彼女に「卵子冷凍作戦は?」と私。ちょうどイギリスで、がん治療や不妊治療目的でなく「キャリア優先のための」卵子冷凍保存が話題になっていたからだ。
その話題の人は独身でITスペシャリストとして働く37歳のテッサさん。
自分の子供は欲しいが仕事が軌道にのる今、キャリアを中断することは考えられず、かといってそうそう後まで子作りを先延ばしするには年齢を考えるとリスクが高い。ということで、今のうちに若い卵子を冷凍保存しておくという選択をしたのだ(なお、イギリスでは2000年にクリニックで冷凍卵子の解凍許可が下り、2002年に初の冷凍保存を経た赤ちゃんが生まれている。この場合は不妊治療の一環としての冷凍)。
もちろん、冷凍保存した卵子が確実な妊娠を保証するものではないが、40、50代いやいや60代でも出産する可能性は残したことになる。キャリア・収入アップ以上に Mr.Right にめぐり合うほうが大変だという意見もあって、子供の産むタイミングをもコントロールしつつ完璧なライフスタイルを築いていく女性。男性諸君、「あなたに出会えたわ、卵子も冷凍保存で準備万端よ」と来る日も近い。テッサさんの場合はシングルマザーになるつもりはないとのことだが、選択肢の広がりとともに、冷凍保存卵子とドナー精子でシングルマザーを選ぶ女性もいるだろう。倫理的に受け入れられる、受け入れられないはともかく、女性の選択肢の幅はここまで広がっているのである。
なお、卵子抽出作業、そして子宮に戻す作業には副作用、ときには命にかかわることも。
また、万が一、本人が死亡した際の卵子のその後を決めておく必要がある。テッサさんの場合はドナー契約にサインしている。また、冷凍作業費用は4000ポンド、冷凍保存料は年間200ポンドなり。高いのか、安いのか……。こうやって書くと生命の誕生に関わる話をしているとは思えず、少々抵抗ありなのだが。
「塾」がいい商売なわけ(韓国:ソウル発)毎年暮れになると必ず思うことだが、1年があっとい間に過ぎて行った。何をしたのかまるで思い出せなかったり、今年も勉強の足りない自分が嫌でたまらなかったりする。しかし、考えてみると、学生の頃は毎日勉強をしていたにもかかわらず「今年は思いっきり勉強したなあ」という実感もない。結局、人は何にも満足できないで生きていくのかも知れない。
さて、今回のテーマは韓国の生徒たちがお世話になっている「塾」の話である。韓国では「塾」と言わず、「学院」と呼んでいる。「学院」は、まったくの私的教育機関であり、そこに通ったからと言って、資格がもらえるわけでもない。つまり、日本でいう「塾」と同じである。内容は、小・中・高対象の「進学塾」や「内申強化塾」、「論術塾」、「TOEFL塾」などと様々である。
進学塾は、日本にもあるように志望校(特需目的高校や自立型高校、大学)の受験向けのもの、内申強化塾というのは大学受験に向けて、現在の高校において内申を強化するための塾、「論述塾」というのは、最近できたもので、大学入試で修学能力試験(センター試験のようなもの)以外に論述試験が重要視されることになり、それに対応するための塾。「トッフル塾」は、これも大学受験で修学能力試験以外に英語の実力を表す数値として提示することができる、トッフルのスコアを上げるコツを教える塾。このように、進学塾だけでまとめられない詳細な部分を教えるのが「学院」である。
韓国はOECD諸国の一員となり、外からみると先進国に見られているかもしれない。しかし、中にいる韓国人たちは依然と中進国ぐらいに思っている。経済的には確かに豊かになったが、教育問題には不満がたくさんある。今年のある調査で面白い発表があった。レストランなどの店がつぶれて、次にできた店は、コンビニや塾が多く、一番長生きする商売が「塾」だというのである。これは、何を意味するのかというとやはり韓国の公的教育に対する親たちの不信感である。
韓国では大学受験の競争が激しいことは、日本のマスコミでも盛んに言われているので、知っている人も多い。だが、なぜそんなに激しいのかがよくわかっていないようだ。韓国では、教育に関しては人一倍関心を持つ親が多い。それは、資源のない国でここまで豊かになったのは人材があったからである。しかし、70年代、80年代の人材というのは、労働力であった。やはり学歴がないとそれ以上の暮らしが望めない人が多く、もともと儒教の教えによって学問が尊ばれてきたこともあり、学歴社会となっていった。学歴のある人たちは、やはり子どもにもいい大学へ入ってもらいたいので、学校の授業以外に塾に行かせて先行学習をさせた。学歴のない親たちも自分たちのせいで、子どもの代もメインストリームからはずされることを嫌い、無理をしても塾に行かせる。そして、普通の暮らしがしたいなら大学にいくことを当然だと思うふしがある。だから、大学受験の競争は激しくなるのである。
テレビを見ていると、貧しい親がいてその人に一番つらいことは何かと聞くと、「お金がないので、子どもを塾に行かせてやれないことが本当に辛い」というシーンを見かけることがよくある。それだけ、塾には行かせたい親がたくさんいるのだ。
韓国の「雁パパ」とは、韓国の中産階級以上の人たちが子ども早期留学させる社会現象から出たことばである。まだ、幼い子どもを一人で留学させるわけにも行かないので、父親は韓国に残って働き、母親が子どもを連れて留学先に行くことである。父親は子どもの将来を考え、仕送りをしながら、一人での寂しさに耐える。いわゆる、家族の将来の幸せを考えた家族の崩壊である。ちょうど日本の男性が子どもの学校のために単身赴任をするのとよく似ている。私の周りにはもっと多くの「雁パパ」たちが出現している。早期留学ではじまった雁パパ生活も子どもが小学生から大学生になるまで、別れて暮らすので仮の独身生活も長くなっており、「雁パパ」は増えるばかりだ。
昨年知り合いの息子さんがアメリカの高校に留学をした。彼女は、もう韓国のわずらわしい受験から開放されてすごく嬉しいと言った。しばらくして、彼女と電話をしたら、「最近は毎日息子の送り迎えで忙しい」という。留学したはずなのにおかしいと思ったら、アメリカが夏休みなので戻ってきていて、その間に韓国の塾で数学や国語などを勉強しているという。その人だけが特別にそうさせているのではなく、早期留学させた人たちは、夏休み、冬休みは韓国に帰国させて塾通いをさせるのが普通だという。それも、評判のいい塾は、予約が取れないくらいだという。お金がある人にもないに人も塾は必要。だから、韓国の塾は息の長い商売である。
※特殊目的高校や自立高校とは、韓国の高校受験はほとんどなく(ソウルには高校受験がない)、有名校以外は内申と住んでいる地域で高校が決まる。しかし、内申1-3%以内の生徒たち向けに全国から募集する特殊目的高校と自立型高校がある。それらは、優秀な人材の素質をさらに伸ばすことに専念しているため、大学受験でも有利なことから、小さい頃からそこに向けての受験勉強が始まる。特殊目的高校は、3種類(科学、外国語、アート)、自立型高校は外国語優秀者を募る。現在、特殊目的高校や自立型高校からはソウル大学など韓国の有名大学だけでなく、海外の有名大学(たとえば、アイビーリーグ、オックスフォードやケンブリッジなど)の卒業生も増えている。
ニューハンプシャーが示したもの
(米国:ニュージャージ発)オハイオで大差の惨敗を喫したヒラリーのニューハンプシャーでの逆転勝利を呼び込んだのは「涙」だった、そう報道されているのですが、それは本当なのでしょうか? 本当に6日の日曜日、投票の2日前にニューハンプシャー州内のカフェテリアで女性支持者と懇談している際に感情的になって一瞬見せた「涙」が勝因だったのでしょうか。
何とも信じがたい話なのですが、どうも本当にそうなのです。この「涙」の一件以降、オバマに先行を許していた支持率がジワジワと戻ってきて、投票日には僅差になっていた、そして投票日当日を通じて「やっぱりヒラリー」という態度を決定した支持者が多かったのだというのです。
まあ、このことに関しては色々な人が色々なことを言っているのですが、大ざっぱにまとめるとこういうことです。まず、5日から6日午前中にかけて行われた各調査機関の「予備選直前の世論調査」では、まだオバマが数%から約10%のリードをしていました。特に、この週末にニューハンプシャーにある名門のダートマス大学で、オバマ支持の大規模な学生集会が行われてそれが報道されたり、5日の昼の時点ではニューハンプシャーの民主党はオバマ一色というムードだったのです。
そこへ「ヒラリーの涙」という報道が流れました。それが全国的に大きく取り上げられる中で、ニューハンプシャーの票も動いてゆくのですが、それはどうしてなのでしょう。ところで、古い価値観の人々の間では「女の涙にはかなわない」とか「女は泣くからやっぱりダメだ」とかいう言い方があります。こうした「決まり文句」の背景には「女性は男性に比べて感情に訴える弱い存在」だという価値観があります。そして「強く理性的な男性が女性を蔑視する、あるいはイヤイヤながら女性に譲歩させられる」時に「女の涙」という言い方がされます。
ですが、今回の一件は全く違いました。勿論、アメリカの場合は女性の人権という考え方が社会全体に完全に浸透しているので「弱い女の涙」というようなニュアンスでの常套句は「政治的に不適切」である以前に、そもそもそんな言い方が消滅しているということもあるでしょう。ですが、ある種のジェンダーの問題は今回の一件では重要な要素だっというのは事実です。
結論から言うと「こんなことでは負けるわけにはいかないわ(意訳すると要するにそういうことです)」と言って涙を見せたことで、女性票が雪崩を打って戻ってきたのです。「うるさいヒラリーもやっぱり女だったのか、可愛いじゃないか」という男性票の動きではなく「余りにも強く立派で、もう遠い存在だったヒラリーも自分と同じ女性だったのね」という女性票の動きが「現象」になったのでした。
その証拠に女性に大変に人気のあるABCテレビの午前のワイドショー「ザ・ビュー」では、バーバラ・ウォルターズやウーピー・ゴールドバーグなどが、この「ヒラリーの涙」を絶賛していたそうですし、例えばヒラリーの地盤であるニューヨークの「タブロイド新聞」では「ニューヨーク・ポスト」も「デイリー・ニュース」もヒラリーの「涙?」の写真を大きく掲載して、しかも好意的なコメントをつけています。
NYタイムスの記事によれば、この「ヒラリーの涙」というのはどうしてインパクトがあったのかというと、ヒラリーはこれまで決して涙を見せたことはないのだというのです。夫が大統領になった初年度に、ファーストレディーとして健康保険制度の改革を進めながら挫折に追い込まれたとき、数度にわたる夫の不倫問題、あるいはホワイトウォーター疑惑など、これまでどんな修羅場でも涙を見せなかった「鉄の女」が今回は人間味を見せた、そこに意味があったというがその解説でした。
面白いのは「涙」の報道が流れた直後に、ヒラリーの陣営からは少し戸惑うような反応があったのだそうです。それが「弱みを見せた」ことになれば勢いについて更にダメージとなる可能性がある、そんな戸惑いがあったそうで、これに関しては陣営の一部から「男性候補が涙を見せても何も言われないのに、女性候補が涙を見せると弱さを指摘されるのは逆差別ではないか」という言い方で予防線を張ろうという動きもあったのです。
ですが、とにかく結果的にこの「涙」はヒラリーに取って圧倒的にプラスになりました。ニューハンプシャーの投票結果を分析した報道によりますと、アイオワの敗戦の際と比較すると、まず「50歳以上の女性の投票率が非常に高かった」つまり、自分たちのアイデンティティを投影する対象としてのヒラリーが危機に陥っている、しかも初めて人間味を感じさせてくれたということで「大変だから行かなくちゃ」という投票行動になったというのです。
更にアイオワではオバマ支持だった40歳代の女性票も「冷たいヒラリーよりは、イケメンのオバマだけど、そのヒラリーが人間味を見せてくれたので、やっぱりヒラリー」というような心理からヒラリー支持に回ったのだと言います。そのヒラリーは勝利集会では、再び「国母の威厳」「鉄の女」という風情で大演説をぶっています。「涙」で勝ったとはいえ、復活した以上は「強い政治家」というイメージに戻してゆこうというわけです。
例えば負けたアイオワでの「敗北演説」では演説の中身こそ強気(「民主党の勝利万歳」で押し通した)だったものの、壇上に夫のビル、娘のチェルシー、ブレーンのオルブライト元国務長官、同じくブレーンのクラーク元NATO軍司令官などを「従えて」グループでの「力の誇示」に走っていましたが、今回のニューハンプシャーでは壇上には「主役の中の主役」ヒラリーが一人で両手を大きく広げて、まあある種たとえて言えば、セリーヌ・ディオンが朗々とバラードを歌い上げるような豪快なポーズでの演説でした。
その内容がまた大変に緻密なレトリックで彩られたもので、例えば一番盛り上がった部分では「ありがとう、ニューハンプシャーの皆さん。あなた方は本当に熱心に私の話を聞いてくれました。おかげで私は私の本来の言葉(ボイス)を取り戻すことができたんです」というような調子です。とにかくヒラリーは「あなた方の声を聞いて、その意見を取り入れて勝った」などとは絶対に言わないわけで、あくまで「良く聞いてもらったので、本来の自分に戻った」というのです。アイオワでの敗北を認めつつも、本来の自分は「強い自分」だというのですから大したものです。
まあこれは、一歩間違えば扇動政治家の世論操作とも言える危険性があるのですが、そこまで言うのは言い過ぎというもので、ここはこの類い希な政治の天才が見せた高度なコミュニケーションのテクニックだという風に見ておくのが正当でしょう。更に冷静に考えると、合衆国大統領というのはどんな逆境においても歯を食いしばって判断を下し続けなくてはならない存在です。
例えば、日本では安倍前首相の突然の辞任が批判を受けましたが、あれは議院内閣制だからまだ許される(許されないながらも、どこか仕方がない)ところがあるのですが、直接選挙(形式的には選挙人が介在するので手続き論としては間接ですが、実態は直接でしょう)によって選ばれる合衆国大統領はあのような形で政権を投げ出すことはできないのです。その合衆国大統領を目指す政治家として、多少目が潤むぐらいの「悔しさ」を見せながらも必死に耐えることで「人格としてのダメージコントロール能力」を見せてくれたというのは、玄人筋からも決して悪印象は持たれてはいないと思うのです。その点で言えば、オバマの方が頭の回転が速すぎてまだ人間的につかみ所がない、そんな見方もできるのかもしれません。
さて、共和党に目を転じますと、こちらは直前の世論調査が予測した通りにジョン・マケイン候補が一位となり、近所のマサチューセッツで知事経験のあるミット・ロムニーは二位になってしまいました。またフロリダなどに張り付いて、真剣に運動を展開しなかったジュリアー二はここでもあまり票を取れていません。
その結果としてどうなるかというと、資金力のあるこの三候補に、中西部で絶大な人気を誇るハッカビーの四者は、まだまだ誰もレースから降りることはないという見方が一般的なようです。ですから、2月5日の「新」スーパー・チューズデーまで、混沌とした状態が続くことになりそうです。心配なのは、共和党の党勢そのものに勢いが見られないことです。今回のニューハンプシャーでも、この州は「オープン・プライマリー」といって無党派にも投票権があるのですが、その中間層の多くがヒラリーとオバマに流れた結果、共和党の総数は低いのです。
また折角勝ったマケイン候補ですが、その勝利演説は「原稿の棒読み」で覇気がなく、このまま全国を勝ち抜いていくようなエネルギーは感じられませんでした。また、苦手な州はどんどんスキップしてゆくジュリアー二は「とにかく全国ベースでの戦いを続けている」と胸を張るのですが、アイオワなりニューハンプシャーの結果が出た時点で、その自分が無視した州民に対して何のメッセージも出さない(まあ出せないとも言えますが)冷たさというのは、50州をたばねる合衆国大統領候補として、どうも真剣味に欠ける印象が否定できません。
そんな中、アイオワではオバマが勝ち、ニューハンプシャーではヒラリーが「カムバック」を遂げるというような「筋書きのないドラマ」を通じて、民主党の党勢はどんどん強まっています。とりわけ両陣営には個人からの献金がどんどん来ているようです。その背景には、勿論、申し上げてきたようなジェンダーや世代の問題があり、それぞれが分断されつつ「今回の選挙が自分の声を政治に反映させるチャンス」だという確信は持っているということがあります。
その「声」というのは「イラク、アフガンの問題」と「環境、エネルギーの問題」におけるブッシュ政権のほぼ全否定に他なりません。バラク・オバマ、ヒラリー・ロッダム・クリントンという不世出の天才政治家が活躍することで、大きな政治的エネルギーが集積されつつあります。そのエネルギーは、アメリカという国を大きく変えてゆくのは間違いないでしょう。
そしてアフガンやパキスタンではアメリカの変化、イギリスの変化などに呼応するように対立していた勢力同士の間で必死に妥協が模索されています。そのような時代の変化を全く無視するかのように、インド洋での給油問題を政治の力比べに「転用」している日本の政治には、アフガン、パキスタンの人々に対する不誠実、いやそれだけでなく、必死に変化を模索しているアメリカ世論に対する不誠実なものすらを感じるのです。
不誠実というよりも、勘違いというべきかもしれません。アメリカが変化しようと苦しんでいる時には、その変化の方向が正しいものとなるように、また変化後のアメリカをどうやって助けるかを考えるのが「同盟」というものではないでしょうか。にも関わらず「過去となりつつある古いアメリカ」との関係にこだわって右往左往するというのは、余程の計算がウラにあるのか、そうでなければ単に愚かなだけなのか、いずれにしても政治のあり方として健全ではないと思います。

